2025年11月10日の衆議院予算委員会で、新NISAを通じた日本の個人金融資産が海外に流出している問題について、激しい議論が交わされました。日本維新の会の斎藤アレックス政調会長が指摘した「NISAはオルカンばかり」という現状に対し、片山さつき金融担当大臣が「個人的には残念」と答弁したことが大きな話題となっています。
新NISAが始まって以来、投資信託の購入データを見ると、約60~70%が海外資産での運用となっているという衝撃的な事実。国民の資産形成は進んでいるものの、その金融資産の大部分が海外流出しているという皮肉な状況が生まれています。この問題は、日本経済の将来にとって看過できない重要な課題となっているのです。
片山さつき大臣「個人的には残念」発言の真意とは
11月10日の国会答弁で、片山さつき金融担当大臣は、NISAはオルカンばかりという現状について「個人的には残念」という本音を漏らしました。この発言は、金融行政のトップとしては異例の率直な表現として注目を集めています。
大臣の発言からは、政府として新NISAの普及自体は評価しているものの、その投資先が海外に偏っていることへの複雑な心境が読み取れます。国民の資産形成と日本経済の成長、この2つの目標の間にジレンマが存在していることが明らかになりました。
堅実なパフォーマンスを選ぶ国民の合理的判断
片山大臣は答弁の中で、オルカンやS&P500が選ばれる理由について「堅実なパフォーマンスを上げている」と認めています。これは、日本の個人投資家が感情論ではなく、実績に基づいた合理的な投資判断をしていることを示しています。

NISAはオルカンばかり!金融資産の海外流出の実態
斎藤アレックス政調会長が指摘したように、NISAはオルカンばかりという現状は数字でも明確に表れています。新NISAの資産残高の約60~70%が海外資産で運用されているという推計は、日本の金融資産が大規模に海外流出している実態を如実に示しています。
・NISA資産残高の60~70%が海外資産
・オルカン(全世界株式)への資金流入額:2024年1~9月で約1.8兆円
・純資産総額:オルカンだけで5兆円超(2025年時点)
・月間資金流入額:最大3,400億円超を記録
特に「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」通称オルカンは、2024年だけで純資産総額が1.8兆円から3兆円超へと急増し、2025年には5兆円を突破しています。この驚異的な成長は、まさにNISAはオルカンばかりという状況を裏付けています。
なぜ日本人はオルカンを選ぶのか
日本の個人投資家がオルカンに集中する理由は明確です。低コスト(信託報酬0.05775%)、究極の分散投資(約50カ国、3000銘柄)、そして過去の堅実なパフォーマンス。これらの要素が組み合わさって、投資初心者でも安心して投資できる商品となっています。
オルカンが選ばれる主な理由
・信託報酬が業界最低水準の0.05775%
・世界経済全体の成長を享受できる
・自動リバランス機能で手間いらず
・為替リスクも分散される
・長期投資で元本割れリスクが低い
斎藤アレックス議員が提案する国内投資優遇策
日本維新の会の斎藤アレックス政調会長は、金融資産の海外流出を問題視し、具体的な対策を提案しました。「国民の貴重な資産が海外のインデックスファンドの購入ばかりに向かい、オルカン、オルカンと最近流行っているが、国内の成長に資する資金が不足している現状を是正する視点を持つべき」と強く主張しています。
海外事例に学ぶ自国投資優遇制度
斎藤議員は、フランスやイタリアの制度を例に挙げて、日本でも同様の仕組みを検討すべきと提案しました。
フランスのPEA(Plan d’Épargne en Actions)
・投資対象をEU域内企業に限定
・5年以上保有で税制優遇
・年間上限15万ユーロ
イタリアのPIR(Piani Individuali di Risparmio)
・投資の70%をイタリア企業に配分義務
・うち30%は中小企業への投資
・5年以上保有で非課税
これらの制度は、国民の資産形成を支援しながら、同時に自国経済の成長にも寄与する仕組みとして機能しています。斎藤議員は「国民の資産形成を自国の成長につなげる、これは世界のひとつの常識」と強調し、日本でも同様の制度設計が必要と訴えました。
片山さつき大臣が示す今後の方向性
片山さつき大臣は、国内投資優遇策について前向きな姿勢を示しました。「国内投資枠が先々あってしかるべきではとか、国内投資をさらに優遇したらという話は出ている」と答弁し、将来的な制度改正の可能性を示唆しています。
特に注目すべきは、大臣が「一番いいのは企業価値の向上から見て、日本株、日本の投信が一番いいと選択されれば一番いい」と述べた点です。これは、制度による誘導ではなく、日本企業の実力向上によって投資を呼び込むべきという考えを示しています。
コーポレートガバナンス改革の必要性
片山大臣は、日本株が選ばれない理由として「コーポレートガバナンス等々の問題がありそうなっていない」と指摘しました。つまり、NISAはオルカンばかりという現状を変えるには、日本企業自体の改革が不可欠だということです。

金融資産の海外流出がもたらす日本経済への影響
新NISAを通じた金融資産の海外流出は、日本経済にとって深刻な問題となっています。国民の貯蓄が日本企業の成長資金として活用されず、海外企業の成長を支える資金となっているという矛盾が生じています。
特に懸念されるのは、この傾向が続けば日本の株式市場の流動性が低下し、さらに日本株の魅力が減少するという悪循環に陥る可能性があることです。
2500万口座を超えたNISAの功罪
片山さつき大臣が言及したように、NISA口座数は2500万を超え、国民の資産形成は確実に進んでいます。しかし、その大部分が海外投資に向かっているという事実は、制度設計時には想定していなかった副作用と言えるでしょう。
NISA拡充の成果と課題
成果
・口座数2500万超で国民の投資意識向上
・老後資産形成の促進
・金融リテラシーの向上
課題
・投資先の海外偏重
・日本企業への投資不足
・円資産の海外流出
なぜ日本株は選ばれないのか?構造的な問題を分析
NISAはオルカンばかりという現状の背景には、日本株市場の構造的な問題があります。過去30年間の日経平均株価とS&P500を比較すると、その差は歴然としています。
1. 長期的な成長性への疑問
2. 人口減少による内需縮小懸念
3. 企業の低収益性(ROE平均8%程度)
4. 株主還元の不足
5. コーポレートガバナンスの遅れ
6. イノベーション不足
これらの要因が複合的に作用し、合理的な投資家ほど日本株を避ける傾向にあります。特に長期投資を前提とする新NISAでは、この傾向がより顕著に表れています。
日本企業の内部留保問題
日本企業の内部留保は500兆円を超えており、これは世界的にも異常な水準です。この資金が設備投資や賃上げ、株主還元に回らず、現金として積み上がっている状況が、投資家から見た日本株の魅力を大きく損なっています。
国民の反応は?SNSで見る賛否両論
国会での議論を受けて、SNSでは様々な意見が飛び交っています。NISAはオルカンばかりで金融資産が海外流出することへの懸念と、投資の自由を守るべきという意見が対立しています。
特に若い世代からは、「日本企業の将来性に期待できない」という厳しい意見が多く見られます。一方で、「国民の資産形成と日本経済の成長を両立させる制度設計が必要」という建設的な意見も少なくありません。
片山さつき大臣の金融政策における実績と課題
片山さつき大臣は、自民党金融調査会の会長を務めるなど、長年にわたって金融政策に携わってきました。新NISA制度の拡充にも深く関与し、国民の資産形成促進に尽力してきた実績があります。
・NISA制度の抜本的拡充を主導
・生涯投資限度額1800万円への引き上げ
・非課税期間の無期限化
・金融教育の推進
・株式市場の活性化政策
しかし、今回の国会答弁で明らかになったように、制度の成功が必ずしも日本経済の成長につながっていないというジレンマに直面しています。
今後の制度改正の可能性と展望
片山さつき大臣の答弁から、将来的な制度改正の方向性が見えてきました。「国内投資枠の設定」や「国内投資への優遇措置」が検討される可能性が高まっています。
想定される制度改正案
1. NISA内に「日本株投資枠」を新設
2. 日本株投資への税制優遇拡大
3. 配当金の非課税枠拡大(日本株限定)
4. 日本株長期保有への特別控除
5. 地方企業投資への追加優遇
ただし、投資の自由を制限することへの反発も予想され、慎重な制度設計が必要となるでしょう。
金融教育の重要性
片山大臣は「金融教育の今の状況も考える」と述べており、国民の金融リテラシー向上が重要な課題として認識されています。日本株の魅力を理解してもらうための教育も必要でしょう。
世界の潮流と日本の選択
斎藤議員が指摘したように、自国への投資を促進する制度は世界的に見て珍しくありません。グローバル化が進む中でも、各国は自国経済の成長を重視した政策を採用しています。
各国の自国投資促進策
・米国:401(k)での米国企業優遇
・英国:ISAでの英国株式優遇
・ドイツ:リースター年金での国内投資促進
・韓国:国民年金の国内投資比率目標設定
日本も、国際競争力を維持しながら、国内経済の活性化を図るバランスの取れた政策が求められています。
投資家として考えるべきこと
NISAはオルカンばかりという現状は、個人投資家の合理的な選択の結果です。しかし、日本経済の将来を考えると、バランスの取れた投資配分も検討すべきかもしれません。

例えば、ポートフォリオの一部を日本株に配分することで、為替リスクの軽減にもなりますし、配当利回りの高い日本株からは安定的な収入も期待できます。
日本企業が取り組むべき改革
金融資産の海外流出を食い止めるためには、日本企業自身の改革が不可欠です。片山さつき大臣が指摘したコーポレートガバナンスの改善は急務と言えるでしょう。
これらの改革を通じて、日本企業が投資家にとって魅力的な投資対象となることが、根本的な解決策となります。
新NISAを通じた金融資産の海外流出は、日本経済にとって重要な課題です。片山さつき大臣の「個人的には残念」という発言は、この問題の深刻さを端的に表しています。今後、国内投資優遇策の導入や日本企業の改革を通じて、国民の資産形成と日本経済の成長を両立させる道を探ることが求められています。投資家としても、短期的な利益だけでなく、長期的な視点で投資先を選択することが重要になってくるでしょう。


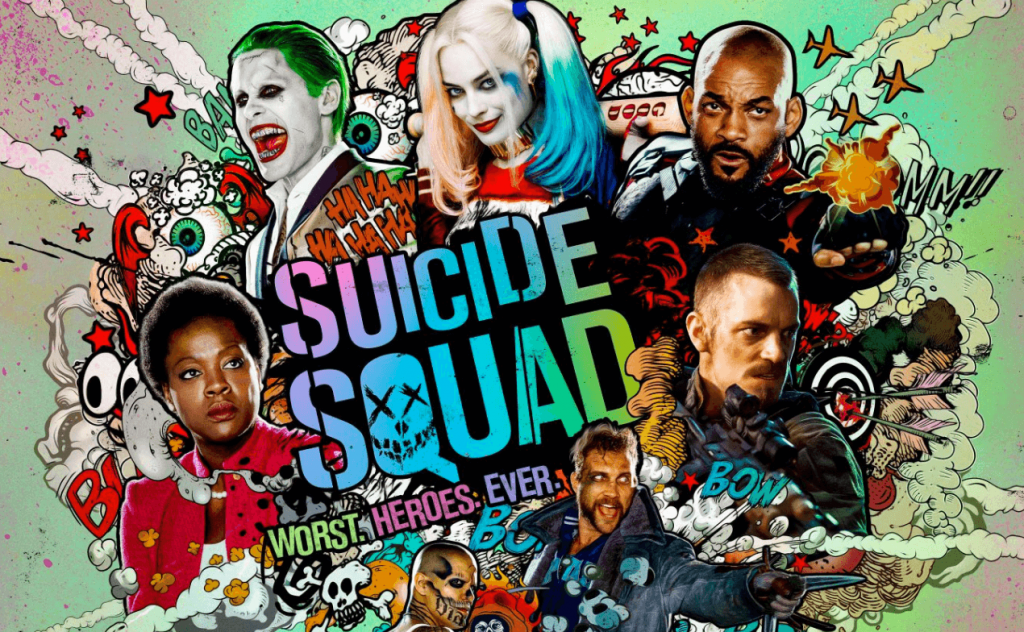

コメント